学科・授業紹介




保育力がぐんぐん育つ楽しい授業

東京福祉大学ではグループディスカッションや発表など、学生が授業に積極的に参加する“アクティブラーニング”を、大学開学当初から実践しています。短期大学部の授業でも、先生やクラスメイトとひとつのテーマについて楽しく話し合うのが基本。自分からどんどん授業に参加できるので、理解が自然と深まります。
グループディスカッションを積極的に取り入れています。小グループでの話し合い、隣の学生との意見交換など、スタイルはさまざま。いろいろな意見にふれて視野をひろげ、柔軟な思考力を伸ばします。

授業では、立って教科書を音読したり、課題レポートやディスカッションの内容を発表したり、さまざまな場面で意見を求められたりします。教員は学生の意見を必ず尊重するので、それが自信につながり、コミュニケーション能力を育てます。

教科書や授業で学んだことを参考に課題の内容をまとめるので、授業の内容が確実に身につきます。レポートの内容は教員がきめ細かく丁寧に指導。がんばった分だけ自分の力になります。

こどもたちは日々の生活や遊びを通して豊かな表現力を身につけます。保育者として、こどもたちの表現力を伸ばすための知識と環境づくりについて学びます。

保育内容(表現)
幼児の造形表現などを学ぶ図画工作

図画工作
こどもの感性や創造性を高める造形表現の世界について理解します。粘土や紙、絵の具などの用具や道具の取り扱い方法などについても学びます。

保育内容(言葉)
こどもの言葉の発達と保育者の役割について学びます。言葉を育てるための絵本・童話・紙しばい等の教材について理解し、読み聞かせの留意点についても学びます。

子作育て支援論
保護者の子育てに関する相談に対して、こどもの専門家の立場からさまざまな知識を生かして支援する方法を身につけます。
短期大学部では、学生たちが学年の枠を超えて先生の研究室に集まり、興味のあるテーマについて少人数で勉強する「ゼミ」が行われています。

手遊びや絵本の読み聞かせ、ミルクのあげ方やオムツの取り替え方など、保育者に必要な実践的な力を養います。

こどもの実態や成長過程にあった保育内容を理解するための知識の他に、子育てに悩む保護者の相談に乗れる力を養います。

紙や粘土、お菓子の空き箱などの身近な素材、絵の具などによる表現活動を通して、こどもたちの学びや発達について理解を深めながら造形活動の実践力を養います。

運動遊びやリズム体操、創作ダンスなどの幼児の体を使った表現やあそびの指導方法などを学びます。

保育士や幼稚園教諭に必要不可欠なのがピアノの技術。毎日の歌の時間やお遊戯など、音楽を必要とする場面で先生が楽しく伴奏してくれるのは、こどもたちにとってとてもうれしいものです。短期大学部では、個々のレベル似合わせて丁寧に指導しますので、段階的に技術を向上させることができ、今まで一度もピアノを弾いたことがない人でも、基礎からしっかり実力がつきます。


保育者の伴奏に合わせて大きな声で元気よく歌ったり、楽器を演奏したりすることは、こどもの成長にとって必要不可欠。本学では1年次から音楽の基礎を学び、ピアノ技術の向上をめざします。
ピアノに全く触れたことがない人には、音符の読み方、手の置き方などの基礎から学習。簡単な曲から少しずつはじめていきます。
授業は初心者と経験者に分かれて指導が行われるので、授業についていけないということはありません。経験者はレパートリーを増やしていきます。
授業の時間以外でも先生の時間が空いていれば、レッスンをしてもらえることも。ピアノ個人練習室も登録しておけばいつでも利用できます。

ピアノは努力を積み重ねていけば必ず弾けるようになります。自分を信じて日々の練習に取り組み、できる喜びを分かち合いましょう。そのために、私たち教員も全力でサポートします。
講師
高木 麻衣子 [たかぎ まいこ]
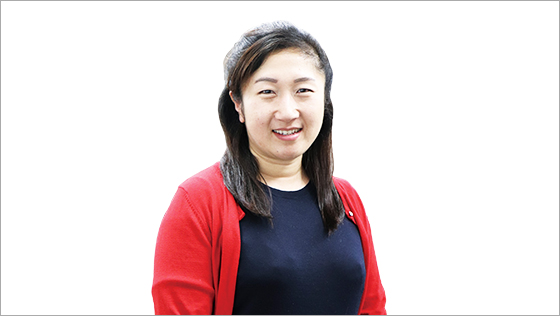
2年間で保育士や幼稚園教諭の免許を取得する短大生は「とても忙しい」とよく言われます。
実際どんな1週間を過ごしているのか、短大生に聞いてみました!